近年、急激な気候変動の影響により、世界各地で自然災害が大規模化しています。地球温暖化の主因とされる温室効果ガスの削減は、国際社会共通の重要課題と言えるでしょう。
この中で、CO2排出量の抑制を目指し、太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーの導入拡大が求められています。電源の非化石化を加速させるため、再生可能エネルギーの普及を後押しする政策としてスタートしたのが、FIP(フィードインプレミアム)制度です。
この記事では、FIP制度の概要からFITとの違い、メリット・デメリットについて解説していきます。
なお、以下では、関東エリアで太陽光パネルを設置しているおすすめの施工業者をまとめているので、参考にしてください。
FIP制度とは?

FIP制度とは、再生可能エネルギーの普及を目的に導入された支援制度です。発電事業者が市場価格に応じて電力を販売することを前提に、一定額のプレミアムを上乗せして収入を得られる仕組みとなっています。
これまで主流だったFIT制度(固定価格買取制度)とは異なり、市場原理を反映しながらも収益の安定性を確保することが可能です。
日本では、2022年から本格的に導入が始まりました。特に法人による大規模な太陽光発電や風力発電に対し、持続可能なビジネスモデルを支える手段として注目されています。
FIP制度が導入された背景

FIP制度の導入背景には、再生可能エネルギーの主力電源化と、電力市場への統合促進が挙げられます。
従来のFIT制度では、固定価格での買取が保証されていたため、電力需給のバランス調整が他の電源に依存していました。そのため、電力システム全体の効率性や持続可能性に課題が生じていました。
FIP制度では、発電事業者が市場価格に応じて電力を販売し、一定のプレミアムを上乗せする仕組みです。これにより、発電事業者は市場の需給動向を踏まえた発電計画を立てるインセンティブが生まれ、電力市場への統合が進むと期待されています。
また、FIP制度は再生可能エネルギーの導入拡大と、新たなビジネスモデルの創出を促進することを目的としています。発電事業者は、蓄電池の活用や発電予測精度の向上などの取り組みにより、収益の最大化を図ることも可能です。
FIP制度とFIT制度の違い

FIP制度とFIT制度では、以下の項目でそれぞれ明確に異なります。
それぞれの違いについて解説していきます。
制度の目的

FIP制度とFIT制度は、いずれも再生可能エネルギーの普及促進を目的としていますが、制度の目的には明確な違いがあります。
FIT制度は、発電事業者に対して一定期間、固定価格で電力を買い取ることを保証する仕組みを採用しています。主に再エネ市場の立ち上げと、投資リスクの低減を図ることを目的として導入されました。
一方FIP制度は、再エネを市場競争の中で自立させることを目指しています。発電事業者は市場価格に応じて電力を販売し、これに一定のプレミアムが加算され、収益を得ることが可能です。
電力の売却方法

FIP制度とFIT制度では、電力の売却方法に違いがあります。
FIT制度では、発電事業者が発電した電力を国が指定する電力会社に対して、あらかじめ決められた固定価格で一定期間売却する仕組みとなっています。発電事業者は市場の価格変動に関係なく、安定した収入を得ることが可能でした。
一方、FIP制度は発電事業者が自ら電力市場に電気を販売し、取引価格に応じた収入を得ることが基本です。その上で、市場価格に一定のプレミアムを上乗せする形で補助を受けるため、市場価格が変動するたびに売上高も変動するという特徴があります。
この仕組みにより、発電事業者は市場の需給に合わせた対応を求められることになり、電力の売却戦略や価格交渉力が重要になりました。
収益の予測可能性
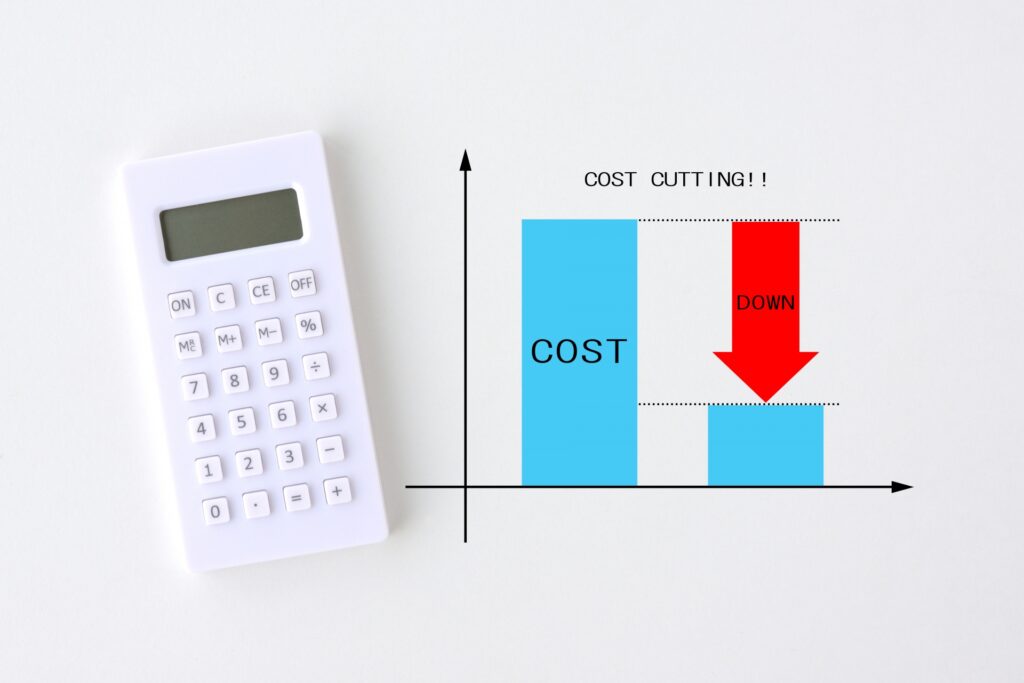
FIP制度とFIT制度の違いの1つに、収益の予測可能性があります。FIT制度では、国が定めた固定価格で長期間電力が買い取られるため、発電事業者は市場価格に左右されることなく、安定した収益を見込めました。
これに対しFIP制度では、発電した電力を市場価格で販売するため、収入は市場の価格変動に影響を受けます。市場価格が下落すれば収益も減少する可能性があり、収益の見通しは常に変動するリスクを伴います。
そのため、発電事業者は市場動向を注視しつつ、発電計画やリスク管理を行う必要があります。結果として、FIT制度に比べFIP制度は収益の予測が難しいのが特徴です。
対象事業者

FIT制度では、小規模から大規模まで幅広い発電事業者が固定価格での電力買取を受けられたため、発電設備を新たに導入する法人や個人であっても、参入のハードルは低く設定されていました。
一方FIP制度では、一定規模以上の発電事業者を対象とし、中規模~大規模の法人事業者に焦点を当てた運用となっています。太陽光発電の場合、出力規模が50kW以上の設備が対象となり、市場取引に参加できるだけの規模と運営体制を持つことが求められます。
この点からも、FIP制度は市場競争力と発電計画の適正管理が可能な法人事業者を主な対象としており、再生可能エネルギー事業の質を高める仕組みであるといえます。
インバランス

FIP制度とFIT制度の違いとして、インバランスの取り扱いが挙げられます。発電量と需要のズレによるインバランスは、FIT制度では基本的に発電事業者の負担とはなりませんでした。
一方で、FIP制度でインバランスが発生した場合、そのコストを事業者自身が負担することになります。そのため、FIP制度ではより高い精度の発電予測や、需要に応じた柔軟な運用が求められ、事業者にはリスク管理能力が不可欠です。
再生可能エネルギーを主体とする法人にとって、このインバランス対応はFIP制度を利用する上で重要な検討事項です。
非化石価値

FIT制度では、発電された電力と非化石価値が一体となり、電力会社に対して固定価格で買い取られていました。そのため、発電事業者が非化石価値を個別に取引できず、価値が市場に反映される仕組みも存在しませんでした。
一方、FIP制度では発電された電力と非化石価値が切り離され、非化石価値を発電事業者が自主的に市場で販売できる形となっています。そのため、環境価値を収益源として活用でき、非化石証書の売却による追加収入が期待されるようになりました。
結果として、再生可能エネルギーの普及促進と市場活性化が図られています。
FIP価格(基準価格)の算定方法
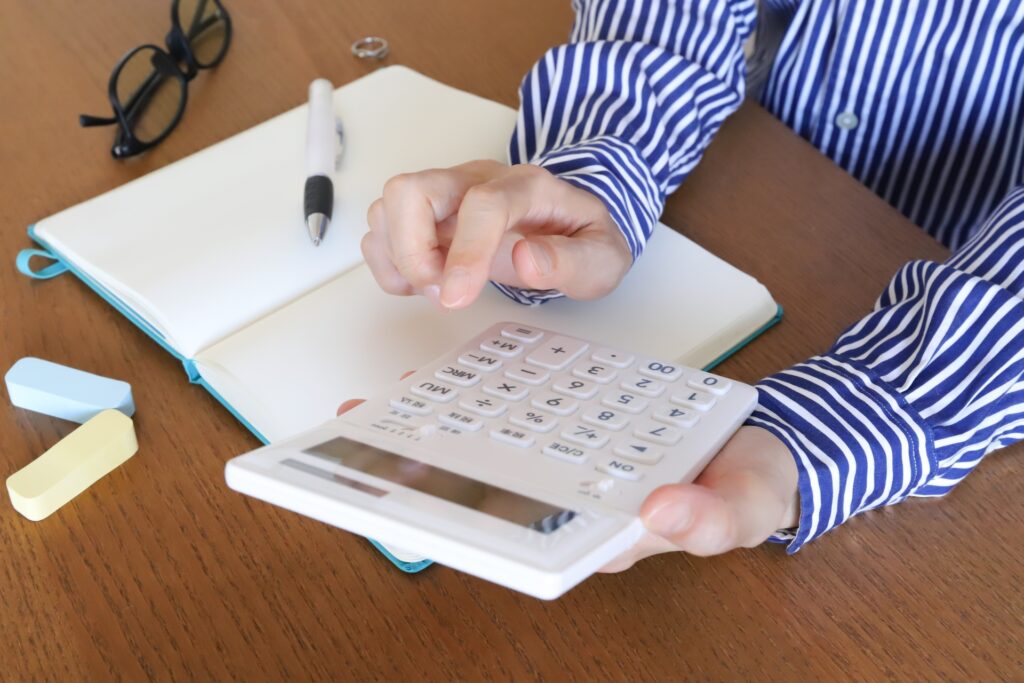
FIP制度における基準価格の算定方法は、以下の計算式が用いられます。
基準価格= 参照価格+プレミアム単価
参照価格とは、発電した電力の平均市場価格を基に算出される金額であり、発電事業者が市場取引によって得られる収入の目安となります。
以下では、FIP価格の計算式にあるプレミアム単価と、算定における重要な要素である「バランシングコスト」について解説していきます。
プレミアム単価とは?
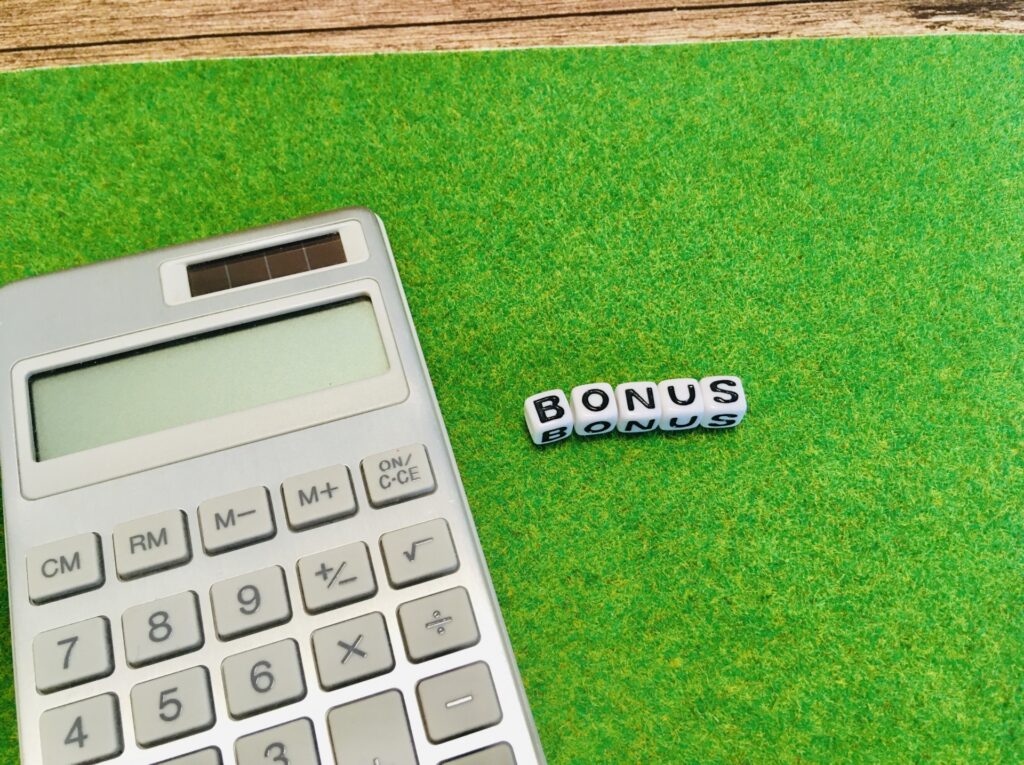
プレミアム単価とは、市場で電力を販売する際に、市場価格に上乗せされる追加報酬のことを指します。再生可能エネルギー事業の採算性を確保し、投資回収を支援するために設定される重要な要素です。
プレミアム単価は以下の要素を考慮し、国が事前に定める仕組みとなっています。
- 発電コスト
- 想定収益
- 事業リスク
発電事業者は市場価格に依存しながらも、プレミアム単価によって一定の収入補填を受けられるため、価格変動リスクを一部軽減できます。特に、大規模な太陽光発電では、このプレミアム単価が事業収益の安定に寄与するでしょう。
バランシングコストとは?

バランシングコストとは、発電計画と実際の発電量とのズレを調整するために発生する費用を指します。再生可能エネルギーは天候など自然条件に左右されるため、事前の発電予測と実際の供給量に誤差が生じることが避けられません。
この誤差を補うため、電力広域的運営推進機関(OCCTO)や電力会社が調整を行い、そのコストを発電事業者が負担する仕組みになっています。
FIP制度では、発電事業者が市場に主体的に参加することを前提としているため、バランシングコストを見積もったうえでプレミアム単価が設定されます。
FIP制度のメリット

FIP制度により、以下のようなメリットが期待されています。
それぞれのメリットについて解説していきます。
市場価格が高いと売電収入が増える可能性がある

FIP制度のメリットとして、市場価格の高騰に伴い売電収入が増加する可能性がある点が挙げられます。発電事業者が市場に電力を供給し、その市場価格にプレミアム単価を加えた収入を得られるのが、FIP制度の仕組みです。
そのため、需要が高まり市場価格が上昇した場合、売電による収入全体も自動的に増加することになります。特に、需要が集中する時間帯や季節においては、高い市場価格を享受しやすくなり、収益性向上につながる可能性があります。
補助制度に依存しない

FIP制度では、補助制度に依存しない発電ビジネスの確立が可能です。市場価格に連動して収益が決まるため、事業者自身が市場の需給状況を読み取り、適切な運営を行う必要があります。
これによって、発電事業者は国の補助制度に依存せず、自立した経営基盤を築くことが可能です。また、プレミアム単価によって最低限の収益は確保されるため、過度なリスクを負うことなく市場参入できる環境となっています。
売電先の選択が自由

従来のFIT制度では、発電した電力は原則として地域の一般電気事業者に買い取られる仕組みでしたが、FIP制度では発電事業者が自由に売電先を決めることが可能になりました。
これにより、電力小売事業者やアグリゲーターと直接契約を結び、市場価格や契約条件に応じた最適な売電戦略を選択できるようになります。発電事業者は、需給状況や相手先のニーズに応じて収益の最大化を図れるため、ビジネスの幅が広がるのです。
また、PPA(電力購入契約)による長期安定契約の締結も選択肢に含まれることで、リスク分散や収益安定化の手段としても活用されています。
蓄電池やEMSも推進できる

FIP制度では、市場価格に応じた電力販売が基本となるため、発電事業者は発電タイミングを調整できる体制を整える必要があります。この過程で、発電した電力を一時的に蓄える蓄電池の導入や、需給バランスを最適化するEMSの活用が促進されるのです。
電力需要のピーク時間帯に合わせて、蓄電池から放電する運用が可能となれば、市場価格の高騰を捉えた収益最大化も期待できます。また、EMSにより発電と消費の最適な制御が実現できるため、バランシングコストの低減にも寄与します。
このように、FIP制度は単なる売電収入の確保にとどまらず、再生可能エネルギーの高度な運用技術の普及にもつながっています。
FIP制度のデメリット
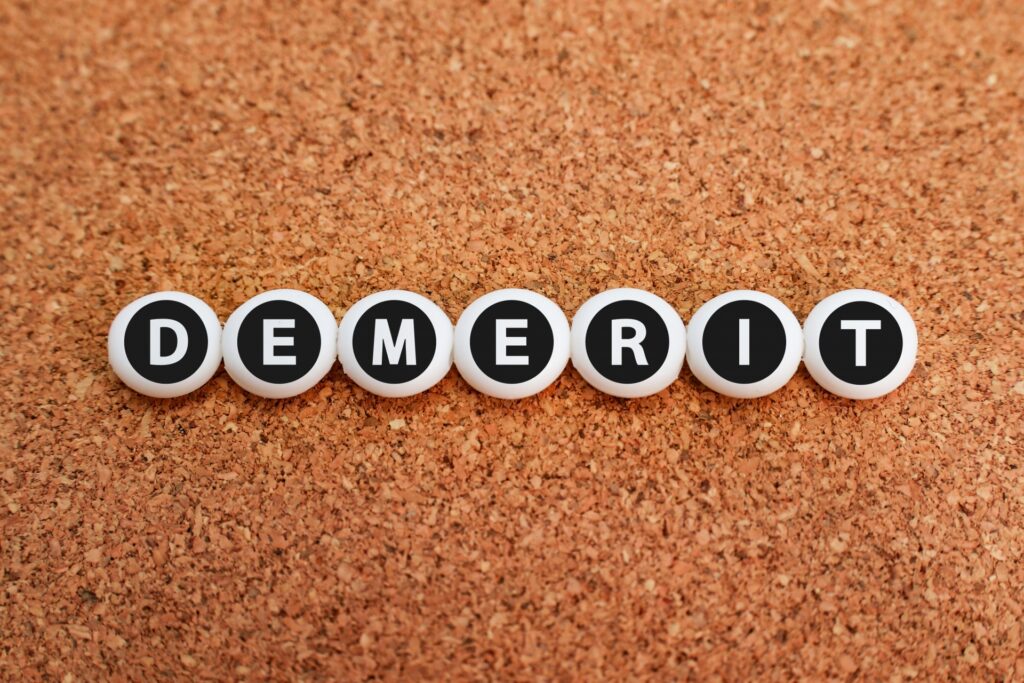
一方で、FIP制度の導入には課題も残されています。具体的には、以下のデメリットが懸念されます。
それぞれのデメリットについて解説していきます。
売電価格が市場価格に左右される
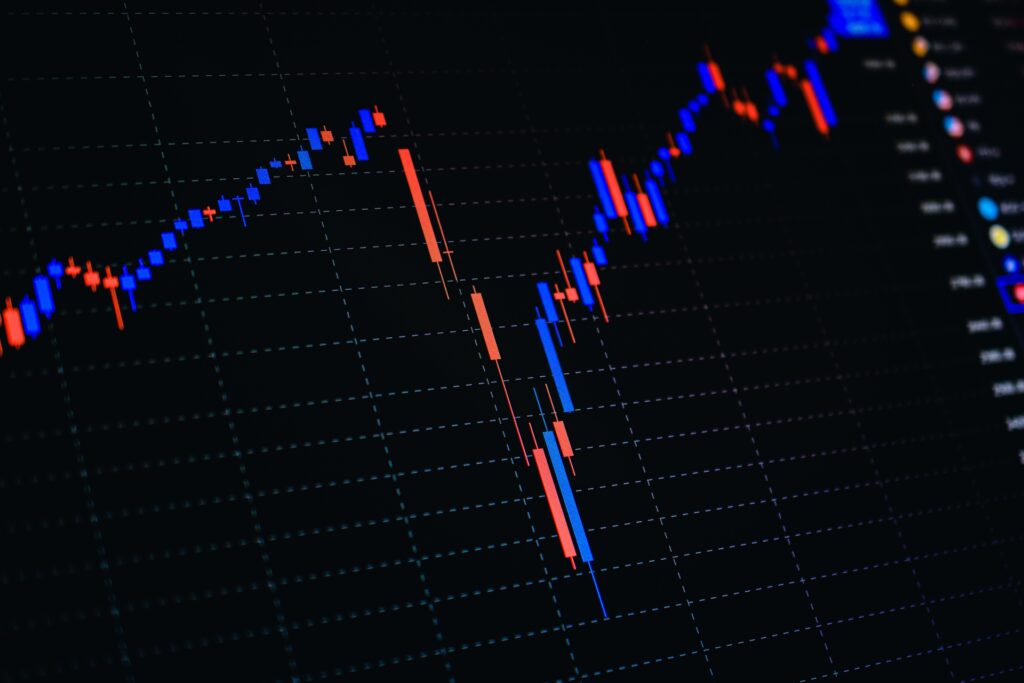
FIP制度のデメリットとして大きいのが、売電価格が市場価格に左右される点です。従来のFIT制度では、発電した電力を固定価格で買い取ってもらえる仕組みだったため、価格変動リスクを考慮する必要がありませんでした。
しかし、FIP制度では市場価格を基準に電力が取引されるため、以下の要素によって売電収入が変動します。
- 市場の需給状況
- 季節要因
- 経済情勢
そのため、発電量が多い日中に市場価格が下落すると、期待した収益を確保できない可能性もあります。
発電事業者は市場価格の動向を常に把握し、収益確保に向けたリスクマネジメントが求められます。価格変動リスクへの対策が不十分な場合、事業運営に大きな影響を及ぼすリスクを抱える点がFIP制度のデメリットと言えます。
制度運用が難しい

FIP制度では、安定した制度運用が難しいとされています。市場価格に連動して収入が変動するため、発電事業者は電力市場の動向を把握しながら売電戦略を立てる必要があります。
これに加え、バランシングコストも自己負担となるため、予測精度の向上やリスク管理が欠かせません。さらに、非化石価値の売却や、プレミアム単価による補填額の変動についても対応が必要です。
FIT制度のように安定した収益が保証されるわけではないため、市場分析やエネルギーマネジメントの知見が乏しい事業者にとっては、収益確保が難しくなるリスクもあります。
運用コストが増加しやすい

FIP制度では、発電事業者が市場で電力を取引することが前提となるため、以下の業務に関する負担が大きくなります。
- 発電計画の策定
- 需給予測
- 売電手続き
また、バランシングコストや取引に伴う手数料なども新たに発生するため、これまでFIT制度に依存していた事業者にとっては、想定以上に運営費用が膨らむリスクがあります。
特に、発電量が不安定な太陽光や風力発電は、正確な発電予測や計画的な運用が求められるため、管理システム・人的リソースの確保が必要不可欠です。FIP制度への移行に際しては、事業計画の策定と運営体制の構築が必須です。
プレミアムの変動・縮小リスク

FIP制度で採用されているプレミアム単価ですが、これは固定されるものではありません。市場環境の変化や、再生可能エネルギーの普及状況に応じて見直される可能性があるため、将来的にプレミアムが縮小されるリスクを抱えることになります。
プレミアムが減少すれば、収益性が低下し、初期投資回収計画に支障をきたす恐れもあります。また、市場価格が上昇した場合にはプレミアムが調整される設計となっているため、想定していた収入が確保できない事態も考えられるでしょう。
したがって、FIP制度を活用する場合は長期的なリスク管理が不可欠となります。
FIP制度の最新動向

FIP制度は2022年4月に導入された比較的新しい制度であるため、最新動向を注視する必要があります。2025年4月時点でのFIP制度の動向としては、以下の3つがありました。
それぞれについて解説していきます。
導入実績の拡大
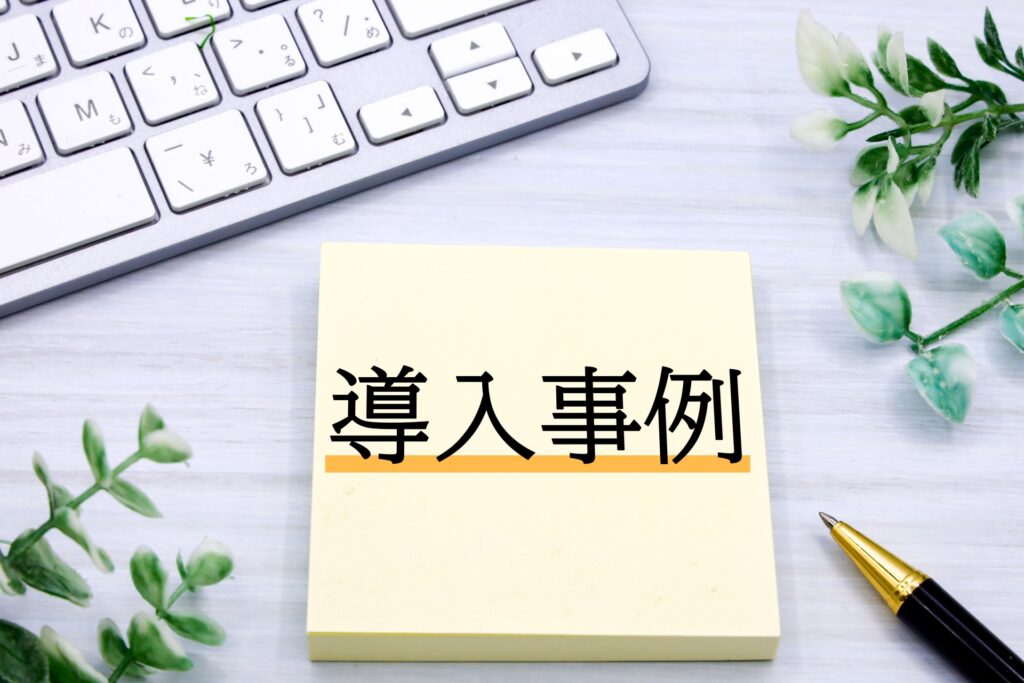
2025年4月時点で、FIP制度の導入実績が着実に拡大していることが確認されています。2023年10月時点でのFIP制度の導入量は、275件・約986MWに達しており、そのうち太陽光発電が最も多く、次いで水力発電やバイオマス発電が続いています。
また、政府はFIP制度の適用範囲を段階的に拡大しており、2022年から2025年にかけて500kW以上、250kW以上の設備が順次FIP制度の対象となり、2026年度以降は50kW以上の設備にもFIP制度の適用が検討されています。
このような政策の進展により、FIP制度の導入実績は今後さらに拡大していくことが期待されています。
初期投資支援スキームの前倒し適用

当初2026年度からの導入が予定されていた初期投資支援スキームは、太陽光発電の導入拡大を促進するため、2025年10月からの適用に変更されました。
このスキームでは、屋根設置型の太陽光発電設備に対し、初期の数年間に高めの買取価格を設定し、その後段階的に価格を引き下げる「階段型価格設定」が採用されています。具体的には、以下のように価格が設定されました。
| 用途 | 価格 |
| 住宅用(10kW未満) | 最初の4年間:24円/kWh5年目以降:8.3円/kWh |
| 事業用(10kW以上) | 最初の5年間:19円/kWh6年目以降:8.3円/kWh |
これにより、発電事業者は初期投資の回収期間を短縮でき、導入のハードルが下がると期待されています。
再エネ賦課金の増加

再エネ賦課金は、FITやFIP制度を通じて再生可能エネルギーの導入を支援するために、電力消費者が負担する費用です。近年、再エネの導入拡大に伴い、この賦課金の総額が増加傾向にあります。
FIP制度では市場価格に応じたプレミアムが支払われるため、電力市場の価格変動が賦課金の増減に影響を与える可能性があります。
政府は、再エネ導入の促進と国民負担の抑制の両立を図るため、入札制度の活用・蓄電池の導入支援など、制度の見直しや補助金の拡充を進めています。
神奈川県でFIP制度の相談におすすめの業者3選

最後に、神奈川県でFIP制度に対応した太陽光発電の販売・施工業者を3つ紹介します。
それぞれの業者について解説していきます。
みらいソリューション株式会社

神奈川県でFIP制度の相談先として、みらいソリューション株式会社が注目されています。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | みらいソリューション株式会社 |
| 所在地 | 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山1-2-1 |
| 電話番号 | 048-764-8969 |
| 公式HP | https://miraisolution-hiroto.com/ |










